「覇王の家」について
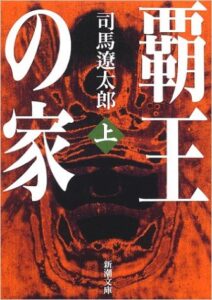
いつもお世話になっております。
今日は、私が私淑している司馬遼太郎氏の名作から、大変印象的な部分をご紹介します。
氏の歴史小説はどれも秀逸で、テイストの異なるものはあるにしても、駄作はないところが素晴らしいところです。
(私ごときが駄作など評価すること自体がおこがましいです)。
今日は徳川家康を取り上げた『覇王の家』の一部分を紹介します。
本能寺の変・賤ヶ岳の戦いのあと、小牧長久手の戦いの前という場面です。
氏が「日本史で一番おもしろい数年間」と別の本で表現しています。
秀吉は、圧倒的な兵力と卓越した外交術をもって、天下統一を果たそうとしていました。九州や四国の勢力は、秀吉の大兵力を見せるだけで、屈服すると思っていたが、家康だけはそうはいかないだろうと思っていた、というくだりです。
「家康は、史上類のない記録をもっていた。二十年近い歳月のあいだ、武田の大勢力に圧迫されつづけ、ときに滅亡の危機に瀕しながらもついに屈しなかったという履歴を持っている。さらに三方ヶ原の戦いにあっては、移動中の武田軍に対し、百パーセント負けるという計算を持ちながら、しかも挑戦し、惨敗した。この履歴は、家康という男の世間に対する印象を、一層重厚にした。」
そのため、秀吉は大領を保有しながら、家康に対して懐柔につとめた、という展開です。このあと、小牧長久手の戦いが始まります。
さすが、江戸幕府を開くだけあって、徳川家康は素晴らしい前半生を送っているし、それに着目した司馬氏の主題設定にもうならされます。
私の前半生において、これに似たようなことがあるとすれば、それは大学時代の体育会空手道部の経験です。
これはつらかった。体が大きいわけでもなく、体力面・技術面で秀でているわけではなかった私に
とって、大学時代の空手道部の4年間は塗炭の苦しみでした。
戦争を経験した世代の人は、二言目には「戦争中は…」と言って若い人を困らせますが、私にとっては、大学時代は戦争に該当する時代でした。
練習も厳しく、飲みも激しい。ザ・理不尽がまかり通る世界です。
(もちろん、自分が上回生のときはそっくりそのまま下級生に理不尽を押し付けていたので、決して嫌いなわけではありません)
当然、上下関係も厳しいですし、人間関係も必ずしもずっと良好というわけではありませんでした。
「今日辞めよう」「明日辞めよう」という毎日でした。
別に、空手で大学に入ったわけではありませんし、体育会をアピールしないと就職できないわけでもありませんでした。
辞めたほうが、恋愛も勉強もバイトも充実したことは間違いありません。
辞めなかった理由はいろいろあります。根性やガッツだけでは説明できません。
いろいろあって、結果として、辞めずに4年間勤め上げました。
(まさに、「刑期を勤め上げる」というイメージです。「足を洗う」とも言いました)
今でも、辞めるか辞めまいかを迷いながら練習を毎日していた頃のことを思い出すと、涙が出てきます。
今でも、辞めて他の道を歩んだほうが良かったかどうかはわかりませんが、この履歴が私という人間の『老舗』につながったことは間違いありません。
途中で辞めないこと、始めたことはガッツで継続すること、これは私の『老舗』です。
また、挨拶をしっかりすること、礼儀を重んじること、先輩を尊敬すること、これもあの場で叩き込まれた私の『老舗』です。
私が新卒で入った興銀という組織はザ・年功序列でしたが、そこだけはまったく違和感なく受け入れられた筆者からは以上です。



